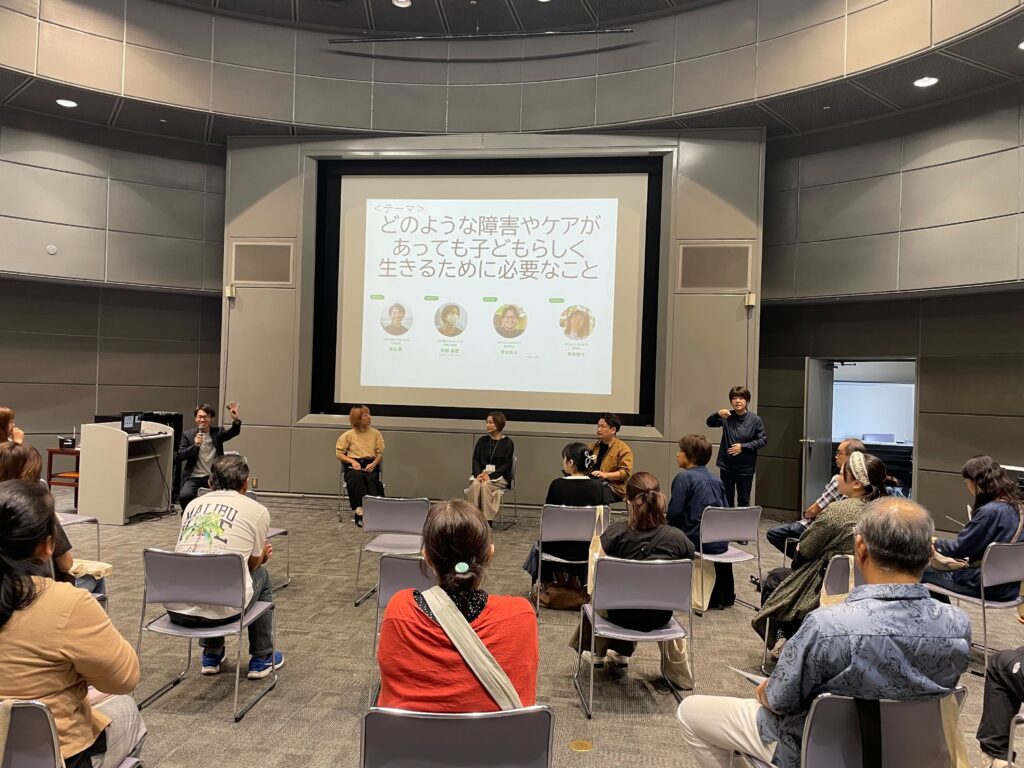「お昼、保育園でのご飯の時間。スプーンやフォークを使っているけれど、食べこぼしが多い子、いませんか?」保育士がそばで見守っても、上手にすくえなかったり、食器をひっくり返してしまったり…。
“どうやって教えてあげればいいんだろう?”と悩む場面、ありますよね。
このとき、どう関わるのがいいのでしょうか?
A:様子を観察して、保育士が使い方を教えてあげる。
B:遊びの中でスコップなど似ている物品操作の練習をする。
C:食べこぼしなく綺麗に食べられる成功体験をつくる。
「あなたなら、どれを選びますか?」
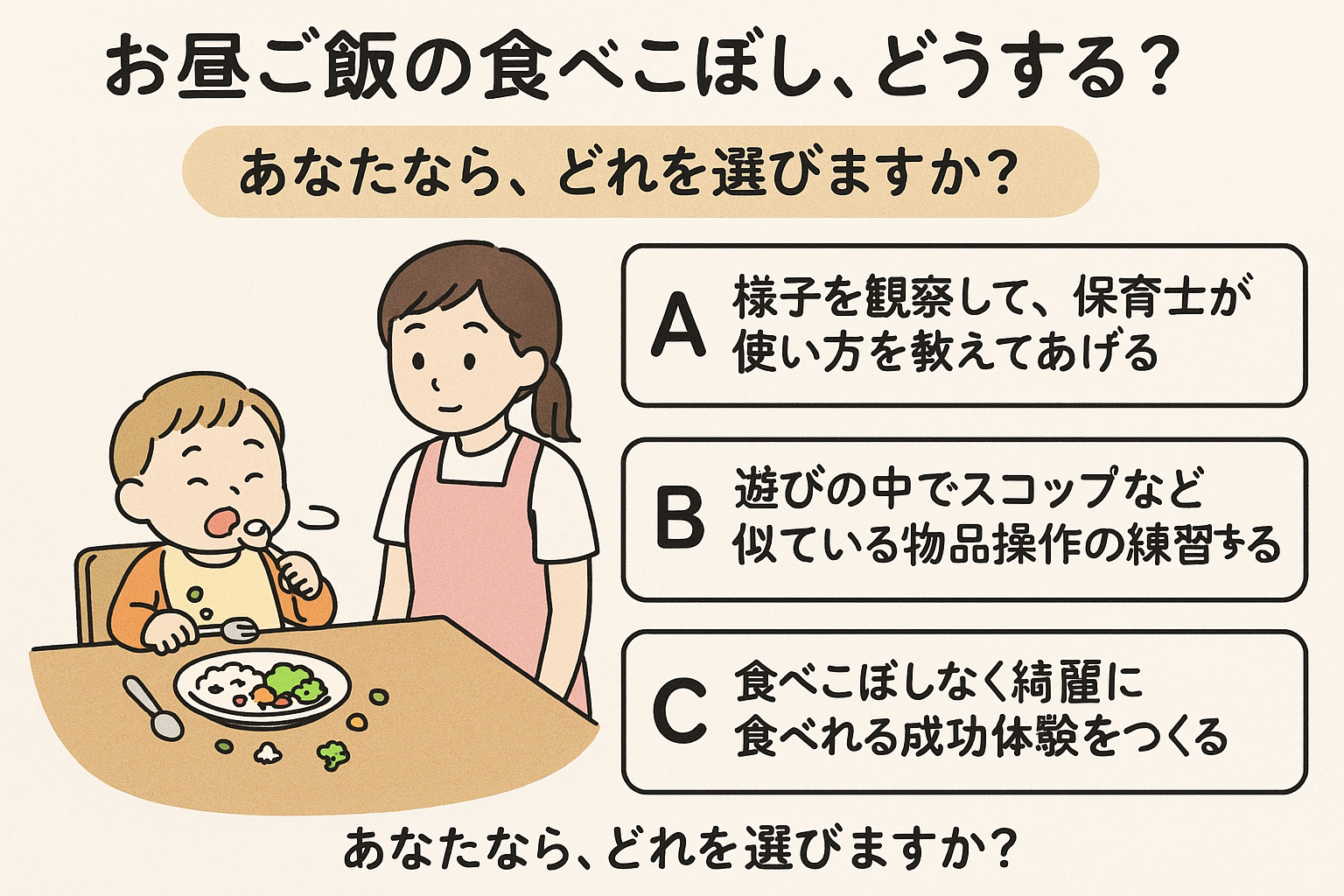
「食べこぼし」は“手の不器用さ”だけではない
食べこぼしが多いと、「手先が不器用なのかな?」と思われがちですが、
実はそれだけではありません。発達が気になる子どもの中には、体の動かし方そのものに苦手さを抱えている場合があります。たとえば、
- スプーンの角度を調整する手首の動きがぎこちない
- すくった食べ物を口まで運ぶ途中でバランスを崩す
- 体幹が弱く、姿勢を支えることにエネルギーを使ってしまう
- 感覚の過敏さや鈍感さで、スプーンの重さや食べ物の感触がつかみにくい
こうした「小さなズレ」の積み重ねが、食べこぼしとして現れます。
つまり、スプーン操作の前に、“体と感覚の準備”が必要なのです。
食べこぼしを減らす3つのポイント
①「すくう動き」を遊びの中で練習する
いきなり食事で上手に使うのは難しいもの。
まずは遊びの中で、スプーンに似た動作を楽しみながら練習しましょう。
- スコップで砂をすくう
- おままごとでスプーンを使って盛り付ける
- ビー玉やスポンジをすくって移す遊び
これらの遊びを通して、「手首の角度」「力の入れ方」「すくう感覚」を育てることができます。
②「安定した姿勢」をつくる
食べこぼしの背景には、「姿勢の崩れ」があることも。椅子の高さが合っていなかったり、机との距離が遠すぎると、スプーンを安定して動かすことが難しくなります。
- 足の裏がしっかり床につく高さにする
- 机と体の間にこぶし1つ分のすき間を
- 肘が自然に曲がる位置でスプーンを持てるように
「姿勢の安定」が、「手の安定」につながります。
③ 成功体験を積み重ねる
大切なのは、「上手に食べること」ではなく、“自分でできた!”という感覚を積み重ねること。最初はスプーンに少しだけのせて運ぶ練習から。
上手にできたら、「こぼれなかったね!」「できたね!」と肯定的に声をかけてあげましょう。失敗を責めず、挑戦を喜ぶ雰囲気づくりが、次の意欲を引き出します。
家庭での練習にも“寄り添いのサポート”を
忙しい朝や夜、ゆっくり見守りながら食事練習をするのはなかなか大変ですよね。特に働くご家庭では、「時間がないからつい食べさせてしまう」
「汚れるのが気になって練習できない」という声も多く聞かれます。
そんなときに頼れるのが、家庭で発達支援も担うベビーシッターです。
ベビーシッターができる「食事動作支援」
仙台を中心に活動する ユニバーサルシッター では、発達が気になるお子さんや、食べこぼしが多いお子さんに対して、「楽しく・自然に」手先を育てる支援を行っています。
🍴 サポート内容の一例
- 食事前の“手や体の準備運動”を一緒に行う
- おままごとやスコップ遊びでスプーン動作を練習
- 食事中に「持ち方」「姿勢」「すくい方」を個別にアドバイス
- 食後の片づけや振り返りを通して「できた体験」を共有
保育園では一人ひとりに十分な時間を割くのが難しい中、シッターは家庭という安心の場で、その子のペースに合わせた支援ができます。
“食べる力”は生きる力|ユニバーサルシッターが大切にする視点
ユニバーサルシッターでは、「食べる=生活の中で自立を育てる行為」ととらえています。そのため、単に「食べこぼしを減らす」ことを目的にせず、
- どうすれば“自分でできる”喜びを感じられるか
- どんな環境で集中しやすいか
- 食事の時間を“成功体験”に変えるにはどうすればいいか
といった、子どもの発達と自信を育てる視点を大切にしています。
まとめ。食べこぼしの裏には“成長のサイン”がある
食べこぼしは、発達の遅れではなく「今、練習中」というサインです。
スプーンを使う力、姿勢を支える力、集中する力、それぞれが少しずつ育つ過程の中に、“できるようになる瞬間”があります。家庭や保育園で工夫を重ねながらも、「もっと丁寧にサポートしてあげたい」と感じたら、
ユニバーサルシッターを活用してみてください。遊びながら手先を育て、食べる楽しさを取り戻すお手伝いをします。“こぼさず食べられた!”という笑顔が、きっと毎日の食卓に増えていきます。
公式LINEはこちら↓
ユニバーサルシッター公式LINE
採用情報はこちら
https://hitoreha.com/recruit/
1回記事 : 「お友だちと遊べない子」への関わり方。発達が気になる子どもの支援と家庭でできること
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds/
2回記事 : 「お友だちを押してしまう子」への関わり方。発達が気になる子の行動理解と家庭でのサポート
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds2/
3回記事 : 転びやすい子、どう関わる?発達が気になる子どもの運動発達と家庭でのサポート
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds3/
4回記事 : 登園しぶりのある子、どう関わる?発達が気になる子どもの朝のサポート法
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds4/