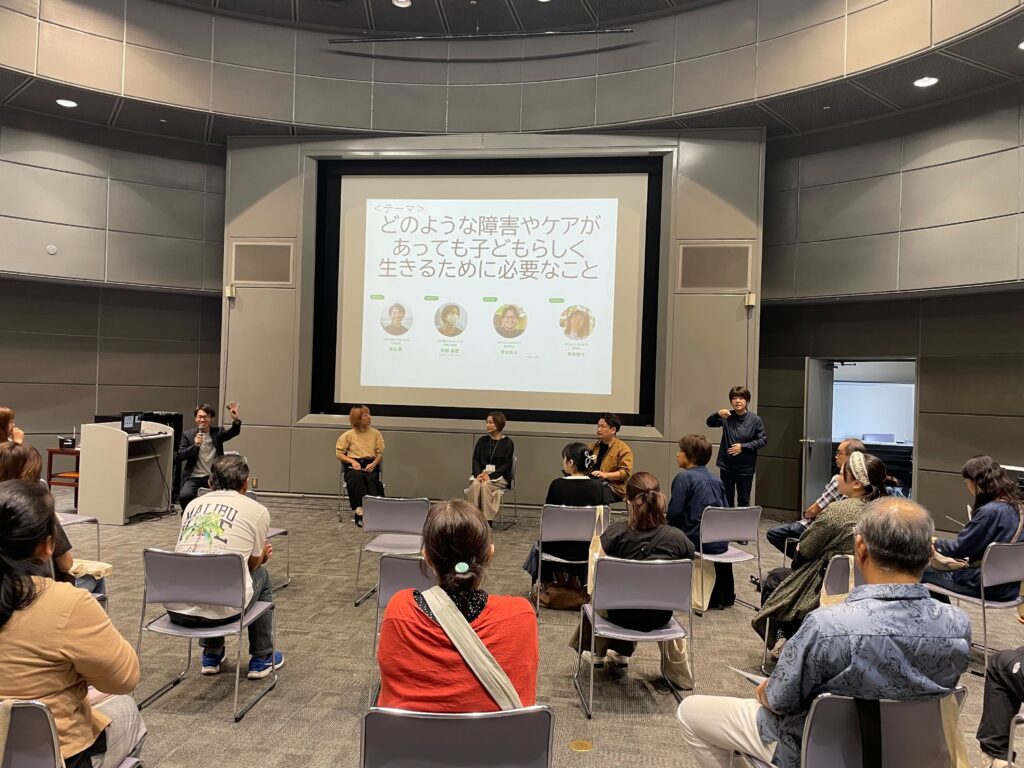「いつも砂遊びばかり、ブロック遊びばかりしている子、いませんか?」
「興味関心の幅が狭く、いつも同じ遊びをしていて、創作するものも同じ。違う遊びに興味を示さず、保育士からのお誘いも聞かない。」
「このとき、どう関わるのがいいのでしょうか?」
A:いつもの砂遊びで道具は違うものを渡す
B:絵本、映像を見せ、反応をみながら違う遊びを提案してみる
C:空間や環境を変えて遊び心を育てる
あなたなら、どれを選びますか?
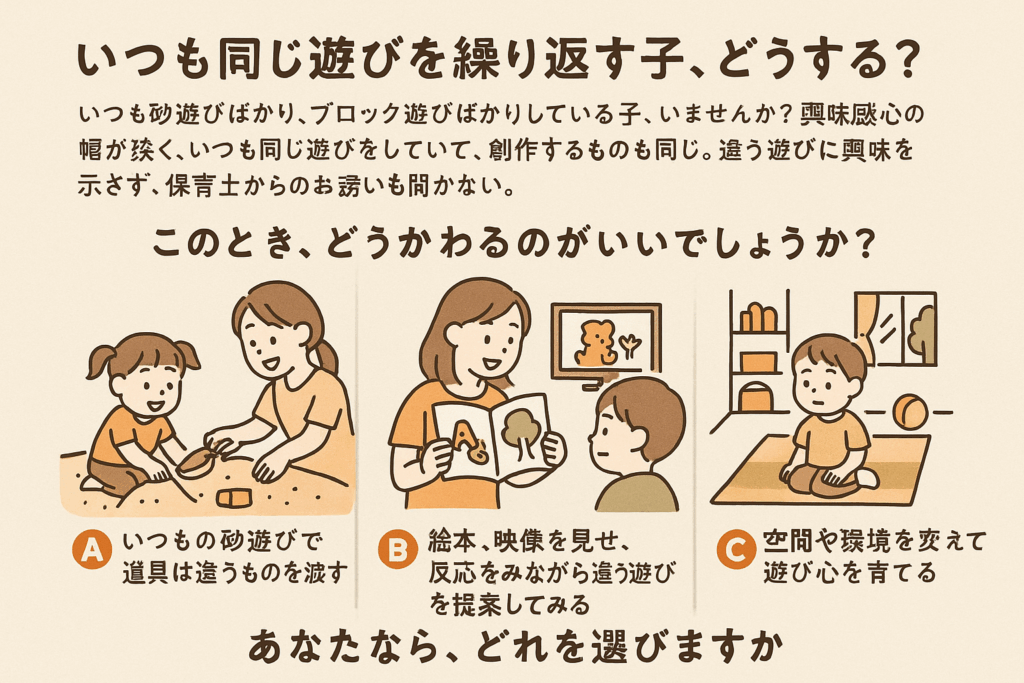
「同じ遊びばかりする」=発達のサイン?
同じ遊びばかり繰り返す子を見ると、「飽きないのかな?」「他のことにも興味を持ってほしい」と感じる保育士や保護者の方も多いのではないでしょうか。実はこの「同じ遊びを繰り返す」という行動には、安心感や発達の段階が深く関係しています。
子どもは「自分の思い通りにできる」「うまくいく」体験を通して、自信を積み重ねていきます。そのため、砂遊びやブロックなど“できる遊び”に繰り返し取り組むのは、自己肯定感を高める行動でもあるのです。
一方で、同じ遊びに固執して他の活動に広がらない場合、「感覚の偏り」や「新しい刺激への不安」など、発達の特性が背景にあることも少なくありません。
「いつもの遊び」に少しずつ変化を加える工夫
子どもが同じ遊びばかりしているとき、無理に別の遊びを勧めるよりも、
“今の好きな遊び”の中に変化を取り入れることが大切です。たとえば、
- 砂遊びなら「カップを変える」「水を足して質感を変える」
- ブロックなら「テーマを決めて作品を作る」「お友達と一緒に作ってみる」
- お絵描きなら「道具を変える」「立って描く・床で描くなど体勢を変える」
このように、今の遊びに“ちょっとしたチャレンジ”を加えることで、
子どもの好奇心が刺激され、興味の幅を広げるきっかけになります。
「遊びの広がり」は“環境”がつくる
実は、子どもの遊びの幅を広げるために最も大切なのは、環境の工夫です。
同じ空間・同じ道具・同じ時間帯の中では、刺激が限られ、子どもも新しい行動に移りにくくなります。たとえば、
- 照明を少し暗くして“探検ごっこ”にする
- 外遊びで拾った葉っぱを工作に使う
- 室内に小さなテントを作り、“秘密基地”のような空間で遊ぶ
こうした空間の変化は、子どもの「やってみよう!」という意欲を引き出すきっかけになります。保育現場だけでなく、家庭でも簡単に取り入れられる工夫です。
「興味が狭い」「関わりが難しい」子への個別サポート
しかし、なかには環境を変えてもなかなか遊びが広がらない子もいます。
それは決して「やる気がない」わけではなく、新しいことに挑戦する力をサポートしてもらう必要があるというサインかもしれません。そんなときに役立つのが、発達特性に理解のある専門スタッフによる家庭支援、それが ユニバーサルシッターです。
「ユニバーサルシッター」とは?遊びの“広がり”を支援する専門的ベビーシッター
ユニバーサルシッターは、発達が気になる子どもやグレーゾーンのお子さんを対象に、一人ひとりの発達に合わせたサポートを行うベビーシッターサービスです。特徴的なのは、「遊びの中で発達を促す」支援方針。
たとえば、同じ遊びを繰り返す子にはこんな工夫を取り入れます。
- 子どもの「好き」に寄り添いながら、少しずつ新しい素材やルールを追加
- 成功体験を積みながら「やってみよう!」という意欲を引き出す
- 感覚や運動面の発達を見立て、遊び方を提案
保育士や療育職経験者が多く在籍しており、専門的な視点で子どもの発達を見守ります。単なる「預かり」ではなく、発達支援+家庭サポートとしてのベビーシッターなのです。
家庭と園をつなぐ“第3の居場所”として
保育園では限られた時間と人員の中で、すべての子に個別対応をするのは難しいもの。一方で家庭では、「どう遊びを広げたらいいのか分からない」という声も多く聞かれます。ユニバーサルシッターは、その中間の存在として、家庭と園をつなぐ「第3の支援の場」を提供します。
マンツーマンで関わるからこそ、子どもの「安心できる関係」の中で新しい挑戦をサポートできる。その積み重ねが、集団生活や日常生活の自信へとつながっていきます。
まとめ。同じ遊びを繰り返すのは、“成長の入口”
「同じ遊びばかりしてしまう」は、子どもが安心して世界を理解している証拠でもあります。大人が焦らず、少しずつ環境や関わり方を工夫することで、やがて子どもは自ら「違う遊び」に一歩踏み出せるようになります。
その“きっかけ”を一緒に作ってくれるのが、ユニバーサルシッター。
家庭での遊びを通して、発達のステップアップをサポートしてくれます。
公式LINEはこちら↓
ユニバーサルシッター公式LINE
採用情報はこちら
https://hitoreha.com/recruit/
1回記事 : 「お友だちと遊べない子」への関わり方。発達が気になる子どもの支援と家庭でできること
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds/
2回記事 : 「お友だちを押してしまう子」への関わり方。発達が気になる子の行動理解と家庭でのサポート
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds2/
3回記事 : 転びやすい子、どう関わる?発達が気になる子どもの運動発達と家庭でのサポート
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds3/
4回記事 : 登園しぶりのある子、どう関わる?発達が気になる子どもの朝のサポート法
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds4/
5回記事 : お昼ご飯の食べこぼし、どうする?発達が気になる子どもの手先サポートと家庭でできる工夫
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds5/
6回記事 : 言葉が出にくい子、どうする?発達を支える家庭での関わり方とベビーシッターの活用法
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds6/
7回記事 : 感覚過敏の子ども、どうする?「嫌がる」には理由がある。家庭でできる関わり方とサポート法
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds7/
8回記事 : 落ち着きのない子ども、どう関わる?集中力を育てる関わり方とユニバーサルシッターの活用法
https://universal-sitter.com/sendai-specialneeds8/