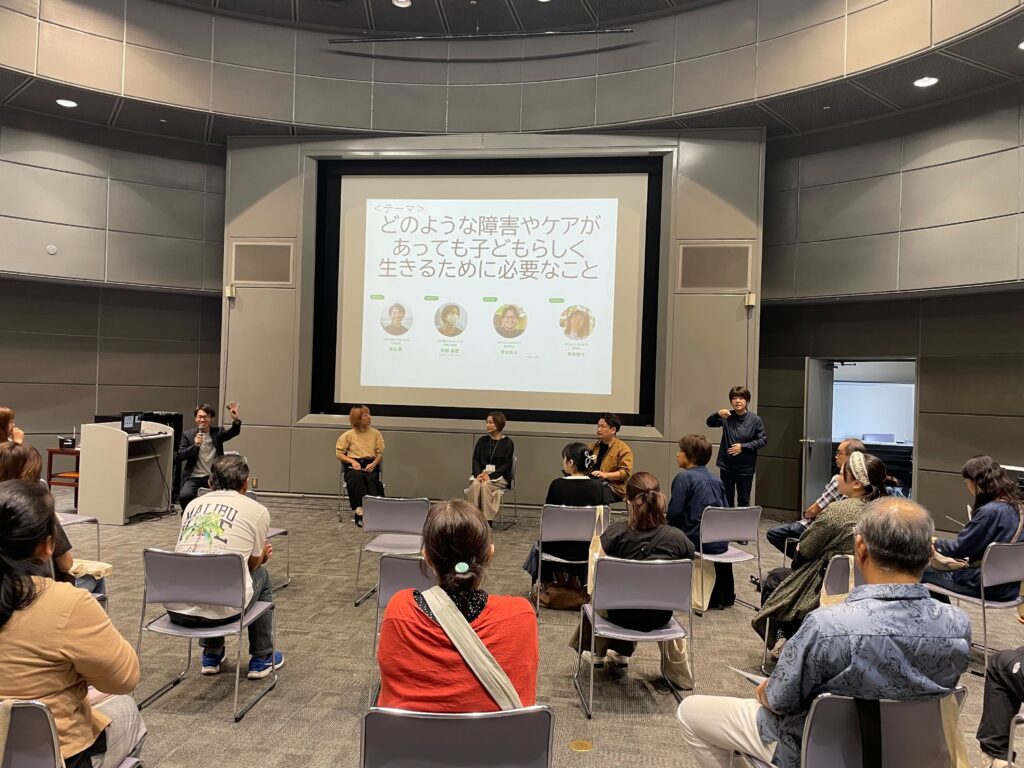就学前準備として、「明日の予定を見て、荷物を準備できる?」
小学校入学を控えた子どもたちは、園生活から大きく環境が変わります。
「明日は体育だから体操服を持っていく」「音楽で鍵盤ハーモニカを使う」そんなふうに、自分で予定を確認し、翌日の持ち物を準備する力が少しずつ求められます。しかし、発達特性のある子どもは、
- スケジュールの把握が苦手
- 見通しを立てるのが難しい
- 指示を聞いてもすぐに行動へ移せない
といった特性があるため、「準備」が大きな壁になることがあります。
では、どのように就学前の準備を進めればよいのでしょうか?

1. 「見える化」で“見通し”をつくる
発達特性のある子どもにとって、“言葉だけ”の説明は理解しにくいことがあります。たとえば、「明日は体育があるよ」と言われても、時間の感覚がつかめず、明日がどのくらい先のことなのか実感しにくいのです。
そこで効果的なのが、「見える化」です。
予定をイラストや写真で示したり、「明日の準備ボード」を使って、
- 体育 → 体操服のイラスト
- 音楽 → 鍵盤ハーモニカの写真
といったように視覚的に伝えると、子どもは「なぜこれを準備するのか」を理解しやすくなります。
視覚的なサポートは、発達特性に関わらず、すべての子どもに効果的です。
2. 「一緒にやる」時間を作り、成功体験を積む
いきなり「自分で準備してね」と任せると、混乱してしまうことがあります。まずは、保護者や支援者が隣に座り、一緒に準備を進めていくことから始めましょう。たとえば、
- 「明日は体育だね。体操服を探してみよう」
- 「上手に入れられたね。明日もそれでOK!」
といったように、できたことをすぐに褒め、準備の流れを“安心できる体験”として積み重ねていくことが大切です。
小さな「できた」が積み重なると、徐々に「自分でもできるかも」という自己効力感が育ちます。
3. 「生活の中で練習する」ことが就学準備の第一歩
就学準備は、特別な課題プリントや机上学習だけではありません。
「準備」「確認」「見通しを立てる」といった力は、日常生活の中で自然に育てていくことができます。たとえば、
- 習い事のバッグを一緒に準備する
- おでかけ前に必要なものを一緒にチェックする
- 翌朝の服を自分で選んで並べておく
こうした日常の中の「準備の練習」が、結果的に就学後のスムーズな生活につながります。
4. ご家庭だけで難しいときは、「個別サポート」を取り入れる
発達特性のある子どもは、理解や行動のスピード、得意・不得意のバランスがとても個性的です。「何度言っても伝わらない」「忙しくて毎日は見てあげられない」そんなときは、家庭の中だけで抱え込まず、専門的な視点でサポートしてもらう選択もあります。
たとえば、ベビーシッターを活用して、家庭での生活スキル練習をサポートしてもらうことも有効です。発達支援に理解のあるシッターなら、遊びの中に自然に「準備の練習」や「スケジュール確認」を取り入れてくれます。
5. 「ユニバーサルシッター」で、家庭の中から就学準備を
発達特性のある子どもと家庭をサポートする「ユニバーサルシッター」では、保育・療育・発達支援の知見をもつシッターが、家庭の中でお子さんの「できる」を一緒に育てていきます。
- 「荷物の準備」や「スケジュール確認」などの日常スキルを、遊びや生活の流れの中で練習できる
- ご家庭のペースに合わせた個別対応ができる
- 保育園や支援機関との情報共有もスムーズ
という特徴があり、保護者の方の「一人で抱え込まない」子育てを実現します。就学を迎える前のこの時期にこそ、「家庭でできる支援」を始めることが大切です。ユニバーサルシッターは、そんなご家庭に寄り添いながら、
お子さんの成長と「安心して送り出せる就学準備」をサポートします。
まとめ:就学準備は“家庭の中”から始めよう
発達特性のある子どもの就学準備では、「予定を理解する」「見通しを立てる」「荷物を準備する」という力を少しずつ育てていくことが大切です。
家庭での生活が、子どもにとって“練習の場”になります。そして、その練習を一緒に支えてくれる存在が、ユニバーサルシッターです。一歩ずつ、自分で「できた!」を積み重ねながら、安心して小学校生活を迎える準備を始めてみませんか?
公式LINEはこちら↓
ユニバーサルシッター公式LINE
採用情報はこちら
https://hitoreha.com/recruit/