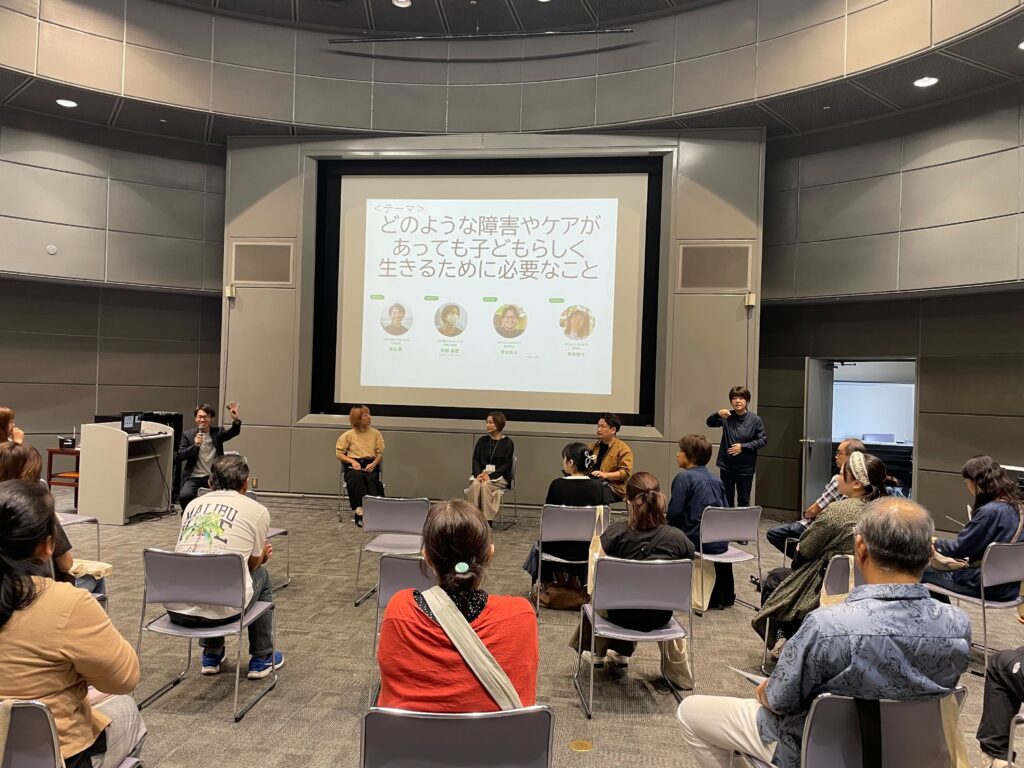「もうすぐ小学校。ひらがなや数字、少しずつ覚えられているかな?」
おうちでひらがなの練習をしていても、なかなか覚えられない子がいます。
同じ文字を書いても形が崩れてしまったり、「あ」と「お」など似た形を混同してしまったり。「いくら練習しても覚えられない…」
「数字が増えると、わからなくなって泣いてしまう…」
保護者の方の中には、「練習すればできるはず」と焦りを感じる方も少なくありません。でも、この“苦手”には、実は発達特性に関わる理由があるかもしれません。

「苦手」は努力不足ではなく、情報処理の特性によるもの
文字や数の理解が難しい場合、単なる「やる気」や「集中力」の問題ではなく、脳の情報処理の仕方に特徴があることが多いです。たとえば、
- 視覚認知(形や空間の把握)が苦手で、文字の形を覚えづらい
- ワーキングメモリ(短期記憶)が弱く、数の順序を維持するのが難しい
- 手先の巧緻性が未発達で、文字を書こうとしても形が安定しない
このような特性があると、何度も練習しても“頭に定着しにくい”のです。
つまり、「頑張っていない」のではなく、「覚え方の方法が合っていない」だけなのです。
「教える」より「感じる」学びを
発達特性のある子どもにとって、効果的な学びの入口は「体験」です。
“書いて覚える”よりも、“触って感じる”“遊びながら気づく”ことが理解につながります。たとえば、
- 文字:粘土で形を作る、砂の上に指で書く
- 数:ブロックやおはじきを使って「数を見える化」する
- 音:リズムや歌で文字や数を楽しく覚える
これらはすべて、五感を使った「体験学習」。遊びながら「わかった!」という成功体験を積むことで、苦手意識が和らぎ、学ぶ意欲が自然と育っていきます。
苦手の克服には「安心できる環境」が欠かせない
苦手なことに挑戦するには、安心できる環境が欠かせません。発達特性のある子どもは、失敗を重ねると「もうやりたくない」という拒否反応を起こしやすくなります。そのため、
- できた部分をしっかり褒める
- 失敗しても責めず、チャレンジの姿勢を認める
- スモールステップで少しずつ段階を上げる
といった関わりが大切です。学校の「勉強」に入る前に、「学ぶって楽しい」と感じられる経験を増やすことが、就学準備の第一歩になります。
家庭だけでは難しい「学びの支援」には、専門性のあるサポートを
「何から始めればいいか分からない」
「勉強を教えると親子でケンカになってしまう」
そんな時は、家庭外の支援を取り入れることも有効です。
仙台市を中心に活動するユニバーサルシッターでは、発達特性を理解したシッターが、ご家庭での生活支援とともに、遊びの中で文字や数への興味を育てるサポートを行っています。具体的には、
- ブロック・積み木・カードを使った“数あそび”
- 絵本やお絵かきを通した“文字への関心づけ”
- 子どもの得意を生かした“学びの入り口”の提案
など、家庭で無理なく取り組める方法を提案します。「勉強」として教えるのではなく、“遊びながら学ぶ”体験を通して学びの基礎を育てることが目的です。
「できない」から「やってみたい」へ。家庭に笑顔が戻る学び方
発達特性のある子どもにとって、学びは「競争」ではなく「気づきの積み重ね」です。周囲のペースに合わせるよりも、その子の理解の形に合わせることが大切です。
ユニバーサルシッターでは、一人ひとりの特性に応じた“学び方”を一緒に探し、「できた!」「楽しい!」という経験を積み重ねていくお手伝いをしています。お子さんが“自分らしく学ぶ力”を育む第一歩を、家庭の中から始めてみませんか?
公式LINEはこちら↓
ユニバーサルシッター公式LINE
採用情報はこちら
https://hitoreha.com/recruit/
1回記事 : 発達特性のある子どもの就学準備。「予定の確認」と「荷物の準備」をサポートする方法
https://universal-sitter.com/syugakumaejyunbi/
2回記事 : 発達特性のある子どもの就学準備。集団生活に必要な「切り替え力」を家庭で育てる方法
https://universal-sitter.com/syugakumaejyunbi2/
3回記事 : 集団での「指示理解」が難しい子へのサポート。発達特性のある子どもの就学準備
https://universal-sitter.com/syugakumaejyunbi3/